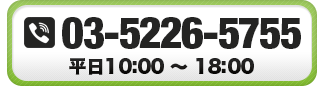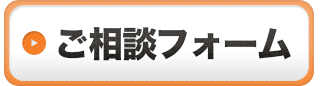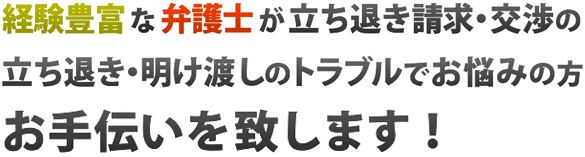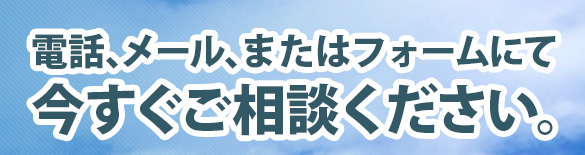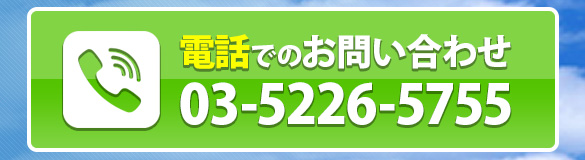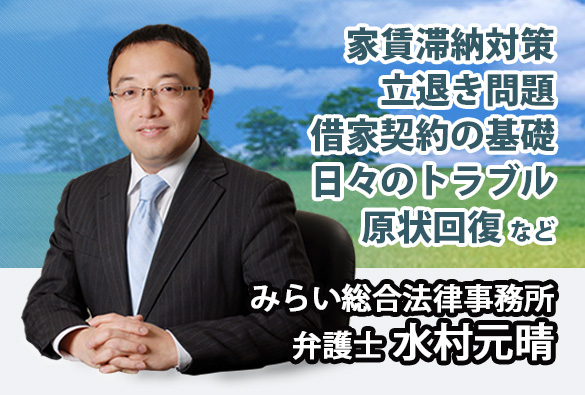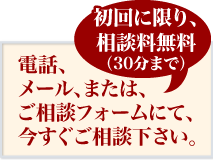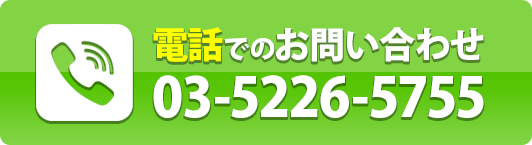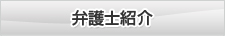賃貸借契約を締結する際に気をつけるべきこと
契約書は必ず取り交わしておく
普通借家契約の場合には、口頭で約束するだけでも借家契約は成立しますが、口頭による約束だけでは、後日「言った、言わない」の争いになってトラブルになりかねないので、普通借家契約であっても契約書は取り交わすべきです。
普通借家契約を締結する際に、最低限、契約書に記載しておかなければならないのは、以下の4点です。
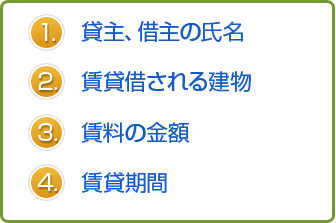
しかし、これらはあくまでも最低限必要な事項です。後々のトラブルを避けるためには、使用目的(居住用か店舗用かなど)、更新料に関する規定、借主の禁止行為に関する規定、契約の解除に関する規定、原状回復に関する規定など、トラブルとなりやすい事項について、できる限り詳細に記載しておくべきです)。
貸す側が気を付けるべきこと
普通借家契約の場合、いったん契約を締結すると、たとえ契約期間が終了したとしても、貸主は正当な理由がない限り契約の更新を拒絶できません。そのような中で、入居が決まった借主がたびたび賃料を滞納するようでは、貸主はそのたびに賃料を督促しなければならず、手間がかかることになります。貸主としては、契約締結にあたり、借主がどのような人物なのか、慎重に見極める必要があります。
そこで、契約を締結する前に、借主から現住所、入居する家族の氏名、職業、勤務先、年収を聞き、借主がどのような人物なのか、事前に確認すべきでしょう。
また、契約締結の際には、借主から住民票(入居者全員分)、源泉徴収票の写しを提出してもらうようにします。さらに、借主に連帯保証人をつけてもらえば、万が一、借主が家賃を滞納した場合には、連帯保証人に請求することができるので安心です。
借主が気を付けるべきこと
まず、契約書には、通常「借家内でペットを飼育することを禁止する」といった、借主が行ってはいけない禁止事項が記載されています。
借主がこのような禁止事項に違反してしまった場合、貸主から借家契約を解除されるおそれがあります。そこで、どのようなことが禁止されるのか、事前に契約書をよく読んで確認すべきでしょう。
また、契約書には「小修繕は借主の負担とする」、「退去時の貸室のクリーニング費用は借主の負担とする」といった、借主の修繕義務や原状回復義務が記載されていることがあります。これらの条項について、内容が抽象的で必ずしも明確でない場合には、どの範囲まで修繕や原状回復を行わなければならないのか、事前に確認しておくとよいでしょう。
貸主から禁止の範囲や義務の詳細を聞き出し、明確にしておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
http://www.mirailaw.jp/
TEL:03-5226-5755
FAX:03-5226-5756
〒102-0083
東京都千代田区麹町2丁目3番
麹町プレイス2階
[地図]
[サイトマップ]